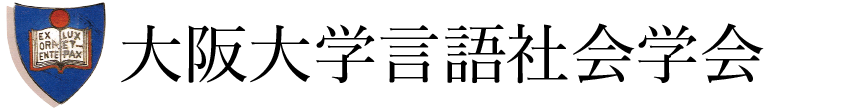役員・規約
Directors/Rules and Regulations
▼ 2025年度役員
▼ 大阪大学言語社会学会 会則
▼ 大阪大学言語社会学会 細則
▼ 大阪大学言語社会学会 学術雑誌投稿要領
▼ 大阪大学言語社会学会 学術雑誌審査規定
▼ 大阪大学言語社会学会 学術雑誌執筆要領
2025年度役員名簿
Directors
| 会長 | 清水政明 |
| 学会誌編集長 | 矢元貴美 |
| 理事 | 上原順一 岡田友和 北岡志織 清水政明 篠原学 進藤修一 中田聡美 中村菜穂 長谷川信弥 福田義昭 古谷大輔 宮下遼 村上忠良 山根聡 矢元貴美 |
| 事務局 | 進藤修一 北岡志織 |
| 大会担当 | 宮下遼 |
| 会計監査 | - |
大阪大学言語社会学会 会則
Regulations of the Association for Integrated Studies in Language and Society, The University of Osaka.
第1条
本学会は、大阪大学言語社会学会と称する。
第2条
本学会は、世界の言語とそれを基底とする社会・文化一般の総合的な学術研究を振興することを目的とする。
第3条
本学会は、次の事業を行う。
- 研究会、講演会の開催
- 学術雑誌の発行
- その他目的達成に必要な事業
第4条
本学会の会員は次の通りとする。
- 正会員 大阪大学の教員(専任・非常勤)ならびに本学会の趣旨に賛同する者で所定の会費を納めた者
- 大学院生会員 大阪大学の大学院生で所定の会費を納めた者
- 学生会員 大阪大学の学部学生で所定の会費を納めた者
第5条
本学会への入会は、所定の入会申込書を提出し、理事会の承認を受けなければならない。
第6条
本学会に総会をおき、正会員をもって構成する。
第7条
本学会に次の役員をおく。
- 会長 1名
- 理事 20名以内
- 会計監査 2名
第8条
理事は総会において正会員の中から選出する。また、会長は理事の互選による。会計監査は、総会において選出する。
第9条
会長は、本学会を代表する。
第10条
理事は理事会を組織し、本会を運営する。会長は理事会の長として会の事業を統括する。会計監査は本会の会計を監査し、総会に報告する。
第11条
会長は理事会の決定に基づいて、毎年1回総会を招集する。
第12条
総会は、出席者の互選によって議長を選出し、次の事項を審議決定する。
- 学会の運営方針
- 学会の予算および決算
- 理事および会計監査の選出
- 学会会則の改廃
- その他学会運営にかかわる重要な事項
第13条
理事会は正会員の中から、理事会の業務を補佐するための委員を委嘱することができる。
第14条
役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
第15条
本会則は、1997年11月6日より発効する。
(2024年9月12日 理事会改正)
大阪大学言語社会学会 細則
Bylaws of the Association for Integrated Studies in Language and Society, The University of Osaka.
第1条 研究活動
- 研究大会を毎年1回開催する。
- 研究例会を開催する。
- 学術講演会を共催、後援する。
- 学会の機関誌を発行する。
第2条
理事会はその下に事務局を置き、委嘱した委員とともに各委員会を組織して学会の業務を行う。
第3条
本会会費は次の通りとする。
- 正会員 年5,000円
- 大学院生会員 年3,000円
- 学生会員 年1,500円とし、学部在籍中は会員資格が維持されるものとする。
第4条
退会を希望する会員は、所定の退会届を提出し、理事会の承認を受けなければならない。ただし大学院生会員および学生会員は、学籍を失った時点で会員資格を失う。また3年以上会費を滞納した会員は、本学会を退会したものとみなすことができる。
第5条
本細則は、1997年11月6日より発効する。
(2024年9月12日 理事会改正)
大阪大学言語社会学会 学術雑誌投稿要領
Academic Journal Submission Guidelines of the Association for Integrated Studies in Language and Society, The University of Osaka.
1. 資格
投稿者は、原則として、大阪大学言語社会学会の会員に限る。但し、当該年度の会費を納入している者に限る。
2. 使用言語
原則として日本語とし、その他の言語の場合には、編集委員会で協議する。
3. 投稿原稿の締切
投稿原稿の締切日は毎年9月20日(必着)とする。
4. 投稿原稿の審査
投稿原稿は「審査規程」に従い、編集委員会の責任において審査を行い、採否を決定する。
5. その他
1) 原稿は他媒体に未掲載または掲載予定がないものに限る。
2) 先行研究や図表の引用・再掲については、法律および社会的な通念に従うものとし、掲載の許可やそれに伴う費用が必要な場合には、執筆者の責任で処理するものとする。
3) 研究倫理については、執筆者の所属機関の倫理を遵守するものとする。
4) 審査の上掲載された論文であっても、表明された見解については、執筆者が責任を負うものとし、大阪大学言語社会学会および編集委員会は、何らの責任も負わない。
5) 本誌に掲載される原稿の著作権は執筆者にあるものとする。ただし、投稿にあたり執筆者は本学会に対し、当該論文の電子化に際しての公開および一般利用者の閲覧・ダウンロードについて著作権(複製権・公衆送信権)上の許諾を与えるものとする。
6) 本誌に発表した論文を他に転載する場合には、事前に書面で編集委員会に通知し、許可を得るものとする。
本規程は、1998年1月22日より施行するものとする。
本規程は、2024年9月12日に改正された。
大阪大学言語社会学会 学術雑誌審査規定
Academic Journal Review Guidelines, The Association for Integrated Studies in Language and Society, The University of Osaka.
1. 大阪大学言語社会学会の発行する学術雑誌に掲載する論文は、原則として本規程による審査を経て、掲載の採否を決定する。
2. 本審査が対象とする論文は、「投稿規程」および「執筆要領」の定めるところに従ったものでなければならない。「投稿規程」および「執筆要領」に従わない投稿は、編集委員会の判断に基づき不受理とし審査対象としないことがある。
3. 編集委員会は、投稿された原稿ごとに、当該分野および関連分野より2名の査読委員を定め、査読を委嘱する。その際、必要に応じて会員以外の研究者に査読を委嘱することができる。
4. 投稿者および査読委員の氏名は相互に匿名とする。
5. 査読委員は、新知見の有無、論述内容や論述形式の妥当性、当該分野における研究への貢献等の審査基準に照らして、論文を審査し、その結果を次に定めるA, B, C, Dの4段階に評価した上で、編集委員会に報告する。
A(そのまま掲載可)、B(一部補筆を求めた上で掲載する)、C(書き直しを求めた上で再査読する)、D(不採用)。
6. 編集委員会は、査読委員からの報告に基づき原稿の採否を決定し、その結果を執筆者に通知する。
7. 査読委員からの報告に基づき、編集委員会の審議の結果、C(書き直しを求めた上で再査読する)と判断された場合、編集委員会は執筆者に原稿の修正を求め、修正された原稿が提出されれば、再査読を委嘱する。再査読と判断された場合、掲載は次号送りとなることがある。
8. 投稿論文の不正(剽窃等)が明らかとなった場合には、当該投稿を無効とする。
9. 本規程は、1998年1月22日より施行するものとする。
10. 本規程は、2024年9月12日に改正された。
大阪大学言語社会学会 学術雑誌執筆要領
Academic Journal Writing Guidelines of the Association for Integrated Studies in Language and Society, The University of Osaka
1. 原稿の種別
本誌には、原稿の種別として、論文、研究ノート、書評を設ける。
2. 原稿の分量
1) 投稿論文は、原則として20,000字以内、最大限28,000字を超えないものとし、書評と研究ノートは16,000字以内とします。
2) 編集委員会の企画による特集論文も、原則としてこれに準じます。
3. 原稿の提出先
1) 原稿は、WordファイルとPDFファイルの両形式で、毎年9月20日までに編集委員会宛にメールで提出して下さい。メール件名は「EX ORIENTE投稿原稿」としてください。
【送信先】大阪大学言語社会学会学会誌編集委員会
info@ou-handai-gensha-gakkai.ac.jp
2) 原稿の提出に先立ち、編集委員会において定める期日までに、投稿希望者は事前申し込みをおこなってください。
4. 原稿の形式
1) 書式
原稿ファイルは、日本語の場合には、原則としてA4サイズ1ページに、1行40字、40行横書きとし、日本語以外の場合も、できるだけこれに準じた形式に設定して下さい。MS-Wordファイルを基本とします。それ以外のファイル形式を希望される場合は、編集委員会にご相談ください。
フォントは、和文にはMS明朝、欧文にはTimes New Romanを用い、10.5ポイントで設定してください。
フッターに通しのページ番号を挿入してください。
本文の冒頭に、タイトルおよびキーワード(3~5語)を記載してください。
2) 図表
図表は本文中の該当する位置に挿入してください。なお、必要に応じて、図表の元データの提出を求めることがあります。図表のキャプション、注記、出典等を明記してください。また、図表を用いる際には全体の字数にご留意ください。
3) 要約
執筆した言語以外の言語により、タイトル、キーワード(3~5語)および、500語(日本語の場合には1,000字)程度の要約を別紙にて添付して下さい。
4) 執筆者情報
別紙に執筆者の氏名(日本語での表記と要約に用いる言語での表記)、ふりがな、住所、メールアドレス、所属(大学、研究科、専攻、加えて、大学院生の場合は課程と指導教員(主・副すべて)名)、執筆言語を明記してください。原稿本文には、執筆者名や所属機関名など、執筆者が特定できるような情報や連絡先などを記載しないで下さい。文中に執筆者が特定できるような記述が含まれる場合、伏せ字としてください。(例:アンケートは○○大学にて実施した。/科研費○○の助成を受けて実施したものである)。また、「拙著」や「拙稿」等の表現も用いないでください。
5. 論文・研究ノートの構成
章、節、見出し、引用・参考文献、注記の表記法は、原則として編集委員会が定めるガイドラインに従ってください。
1) 本文をいくつかの節に分けて、1. 2. 3. … のあとに、見出しをつけてください。節を項に細分化する場合には、1.1、1.2、1.3 … のあとに小見出しをつけてください。
2) 原則として当用漢字、現代かなづかいを使用してください。
3) 本文中の英数字は原則として半角を使用してください。年号、月日などは、原則としてアラビア数字を使用してください。年号は原則として西暦を使用してください。
4) 初出の外国人名、外国の地名など固有名詞は原則としてカタカナ書きのあとに( )内に原語もしくはローマ字転写を付してください。
5) 脚注をつける場合には、本文の末尾にまとめて通し番号をつけ、本文中の脚注を挿入する箇所の右肩に上付き文字で、当該の番号1. 2. 3. … を記入してください。
6) 本文・注等における引用文献は、脚注として記載するのではなく、文中の該当箇所に、和文では全角、欧文では半角のかぎ括弧[ ]を付け、著者名、刊行年、引用ページの順に下記の例に従って記載してください。
[丸山 1960: 67-69]
[Clarke 1990: 123]
[丸山 1960: 67-69; Clarke 1990: 123]
7) 本文および注で指示した文献は、原稿の末尾にまとめて、下記の方法で記載してください。
文献は、著者の姓のアルファベット順または五十音順に配列してください。同一著者の文献は、刊行年の順に配列してください。また同一著者同一年の文献は、出版年の後ろにアルファベットa, b, c … を付け、区別してください。
論文は、著者名、刊行年、タイトル、雑誌または書籍名、巻号、掲載ページを記載してください。書籍は、著者名、刊行年、タイトル、出版社、出版地を記載してください。和文文献の場合は、書名・雑誌名を『 』で、論文名を「 」でくくってください。欧文文献の場合は、書名・雑誌名をイタリック体で記載し、論文名を “ ” でくくってください。
インターネット上の情報を利用する際は、サイト名、URL、閲覧日を記載してください。
丸山眞男 1947 「福沢諭吉の哲学」『国家学会雑誌』61(3),255-256。
丸山眞男 1961 「思想史の考え方について――類型、範囲、対象――」武田清子編 『思想史の方法と対象――日本と西欧――』創文社,東京,311-315。
丸山眞男 1992 『忠誠と反逆――転形期 日本の精神史的位相――』筑摩書房,東京。
Clarke, Peter 1972 “Electoral Sociology of Modern Britain”, History, 57, 31-55.
Clarke, Peter 1983 “The Politics of Keynesian Economics, 1924-1931”. In Micheal Bentley and John Stevenson (eds.), High and Low Politics in Modern Britain, Clarendon Press, Oxford, 152-181.
Clarke, Peter 1996 Hope and Glory: Britain, 1900-1990, Allen Lane / The Penguin Press, London.
Goldberg, Adele 2019 Explain Me This: Creativity, Competition, and the Partial Productivity of Constructions, Princeton University Press, Princeton.(アデル・E・ゴールドバーグ著,木原恵美子・巽智子・濵野寛子訳 2021 『言えそうなのに言わないのはなぜか――構文の制約と創造性――』ひつじ書房,東京。)
文部科学省 2015 外国人児童生徒のための就学ガイドブック,https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/clarinet/003/1320860.htm,閲覧日:2024年9月9日。
SIL Philippines (n.d.) Mangali and Tanudan Valley Music, https://philippines.sil.org/resources/audio_and_video/mangali_and_tanudan_valley_music, Accessed September 9, 2024.
6. 校正
1) 執筆者による校正は原則として2校までとします。
2) 論旨にかかわらない字句および体裁については、編集委員会の責任で修正を行うことがあります。
7. その他
執筆者の母語以外の言語による原稿は、信頼できる母語話者の校閲を受けてから提出してください。
(1998年1月29日編集委員会決定)
(2013年12月20日編集委員会改正)
(2024年9月12日編集委員会改正)
(2025 年5 月8 日編集委員会改正)